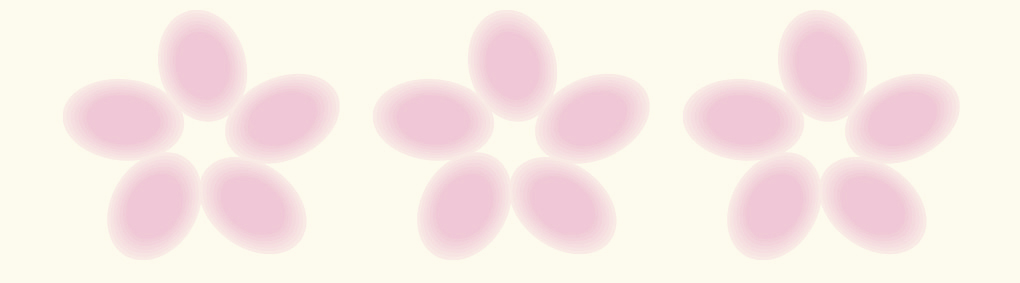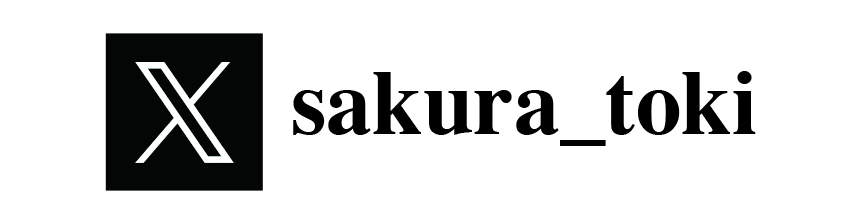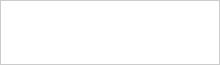土曜日の午後にブログを書いています。
この1週間、様々なニュースが飛び込んできましたね。
さて今日は、中小企業診断士の資格の活かし方について書きます。
最近、資格を取得されたばかりの方からご相談をいただいたのと、
同様な相談を時々いただくからです。
私自身も、資格を取ったものの、どう活かしてゆけば良いか悩みました。
中小企業診断士という資格は、経営コンサルタントの唯一の国家資格といわれだけに
経営を理解するために幅広い学習が必要です。
その分、特定の分野に特化しているわけではなく、独占業務がない資格です。
ですので、資格をどのように活かすかは自由に設計できます。
最もやりやすいのは、それまでの実務経験を強みにしてコンサルティングをすることです。
コンサルティングだけでなく、セミナーや研修講師、執筆にも挑戦できます。
会社にお勤めしている人は、土日を使ってボランティアで活動する人も多いです。
このような活動をプロボノといいますね。
中小企業診断士の資格は、一定の要件を満たせば一生使える資格です。
このため、短期的には実務経験を活かし、中長期的には専門分野を自分で決めて学ぶことで
提供できるサービスの幅を広げることができます。
私の場合は、会社員時代に製品開発や販売促進、広報をしていましたので、
独立当初は、そうした分野を専門にしましたが、資格取得後も様々な資格を取得し、
他の資格と組み合わせてお仕事を広げました。
たとえば最初に取得したのは事業再生に係る資格です。
金融機関の方であれば、もともと財務の知識があり、資金調達の実務経験をお持ちなので、
「財務知識×資金調達実務×事業再生ノウハウ」という3つの要素を組み合わせれば特徴が出ますね。
ただ、金融機関出身の中小企業診断士は大勢いますので、差別化するためにはもうひとひねり必要かもしれません。
例えば、総務経験しかないという方であっても、総務の仕組みを理解されているだけで
大きな強みになると思いますし、「総務経験×IT知識×生産性向上」といった具合に
知識を追加することで稼げるコンサルタントになれるかもしれません。
こういうお話をすると「あんなに勉強したのに、また勉強しなければならないんですか~」と言われますが、
学習習慣ができたからこそ、途切らすことなく学び続けることが大事ではないかと思います。
ノーベル生理学医学賞受賞した大阪大学の坂口志文特任教授に続いて京都大学の北川進特別教授が化学賞を受賞されましたね。
不断の努力の結晶だと思いますが、ノーベル賞は無理でも、誰でも一生学ぶことはできると思います。